校長室から『自ら学び始める子どもを育てる~職員で自由進度学習を研修~』
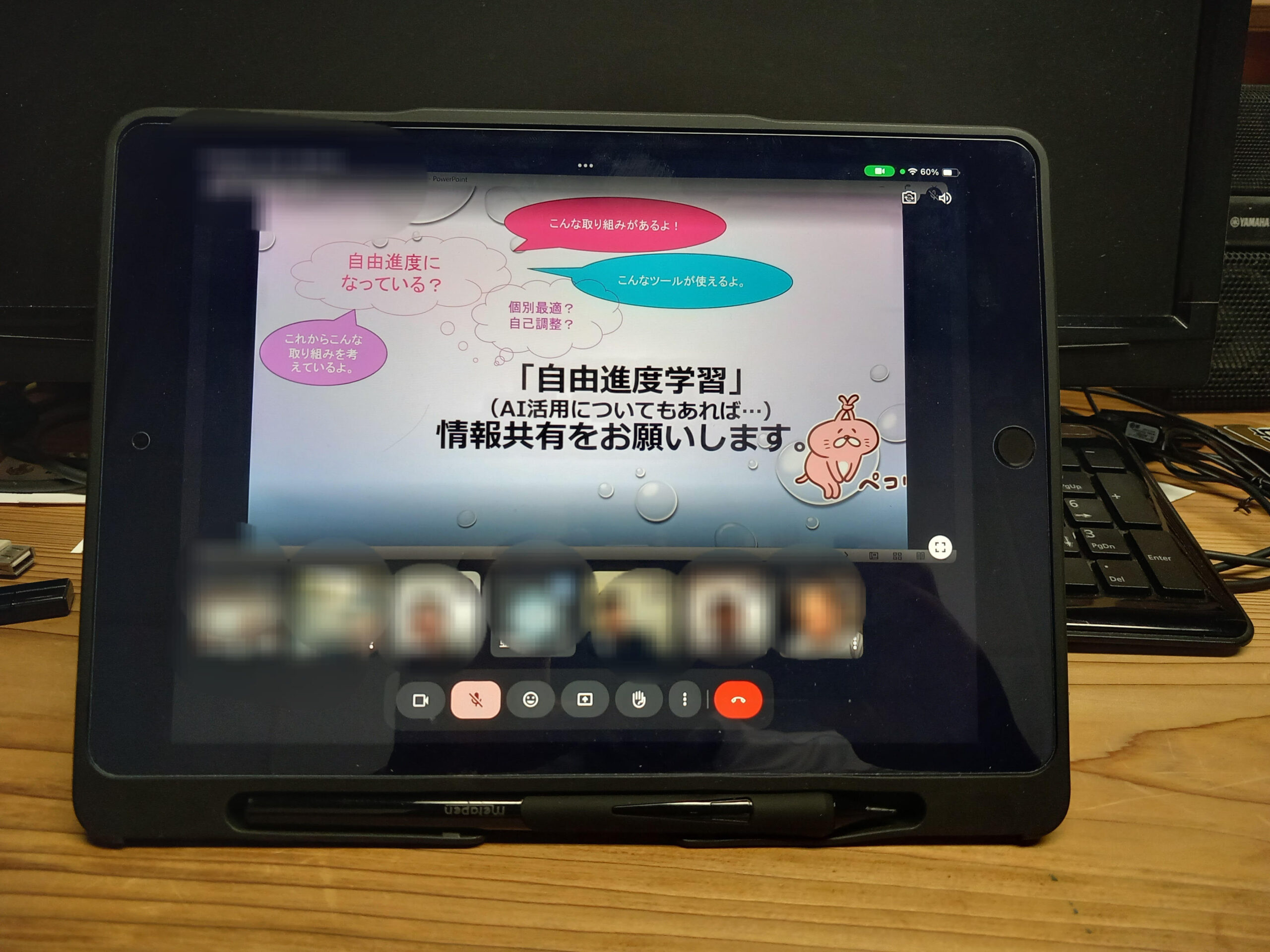 先週の職員研修では、“自由進度学習”について職員同士で学び合いました。“自由進度学習”とは、同じ教材を使いながらも、子ども一人ひとりが自分のペースで学習を進める方法です。理解の速さや得意・不得意に合わせて取り組むことができ、得意な子はどんどん先に進み、苦手な子は立ち止まってじっくり取り組めるといったように、それぞれに合った学び方を実現できます。めます。そして何より大切なのは、学び方やスピードを自ら選択し、計画できることです。
先週の職員研修では、“自由進度学習”について職員同士で学び合いました。“自由進度学習”とは、同じ教材を使いながらも、子ども一人ひとりが自分のペースで学習を進める方法です。理解の速さや得意・不得意に合わせて取り組むことができ、得意な子はどんどん先に進み、苦手な子は立ち止まってじっくり取り組めるといったように、それぞれに合った学び方を実現できます。めます。そして何より大切なのは、学び方やスピードを自ら選択し、計画できることです。
この“自由進度学習”は小学校から始めておくべきだと考えています。私の娘の例ですが、中学校の時、国語の成績が伸び悩んでいました。「何をすれば成績が向上するか」と尋ねると、「新聞を読む」「本を読む」と答えました。確かに関連はありますが、中学生から始めるのでは遅いのです。私は学習の振り返りや問題集を計画的に進めるよう助言しましたが、本来は自分で考えて計画する力が必要です。その時、娘が学び方を身につけられてない、もしかしたら学び方を教えてもらっていないのではないかとさえ思いました。
コロナによる休校時には、この「学び方を学んでいない」現実を全国の先生方が痛感しました。タブレットも通信手段も乏しい中、数カ月間家庭で過ごした子どもたちの学びは止まりました。保護者から「家で遊んでばかりいる」との声が寄せられ、先生たちは慌ててプリントの宿題を作成しました。しかし、ごく一部ですが、学び方を学んでいた子は自走していたはずです。この経験から、「子どもが自ら学べるように学び方を変えよう」という声が全国で高まりました。その一つが“自由進度学習”です。
今回の研修では、私が昨年度担当した3年生算数の実践も紹介しました。それは、3年生の学習内容に加えて4・5年生の発展的な内容も示し、子どもたちに学習計画を立てさせました。理解が速かった二人は、期間内に上位学年の内容まで学び、しっかりマスターしていきました。問題を解くだけでなく、教科書の内容をまとめたり、オンデマンド教材を活用したりして学びを深めました。こうした経験の積み重ねが、先生に頼らず自ら学び進める子を育てるのだと思います。
研修では、英語科での取り組みが紹介されました。弱点を見つけて予習・復習に活かす実践です。“自由進度学習”も同じで、大切なのは自分の力量や特性を把握することです。例えば「読むのは得意だが作文は苦手」「語彙力が不足している」といった原因を自覚しなければ、学びを進められません。
国語科では、漢字習熟に自由進度を取り入れていました。記憶には個人差があります。1回で覚えられる子もいれば、何度も練習が必要な子もいます。それを考慮せず一斉に漢字ドリルを課すと、記憶力の高い子には単なる作業になり、時間のかかる子には定着しないまま次の漢字に進むことになってしまいます。
自由進度を意識した学習方法は少しずつ広がっていますが、その基盤は一人ひとりの意欲です。「できるようになりたい」「わかるようになりたい」という気持ちがなければ成立しません。意欲が少ない子にとっては、“自由進度学習”は荒野に一人放り出されるようなものです。その場合、先生が課題を与え、「今日はここまで」「宿題はこれ」と具体的に指示しながら、少しずつ自由進度の取り組みに挑戦させる必要があります。
こうした個に応じた対応の違いをつけられるのは、超小規模校という本校の強みです。今後も積極的に取り組んでいきたいと思います。
テヘラン日本人学校で学ぶ子ども達へ
せんせいからしじされるのではなく、じぶんでがくしゅうをすすめられるこになっていきましょう。
